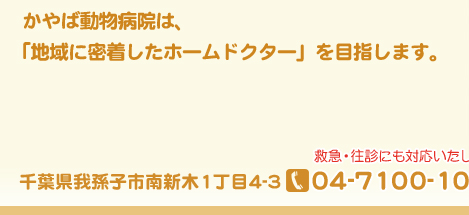※診療内容と料金を併記することは法律により禁じられています。
お問い合わせはお手数ですがお電話か窓口にてお願いします。
犬、猫を飼い始めたけど、「何をしてあげればよいのかよくわからない」という方のために、
飼主さんが愛犬、愛猫にしてあげられる(してあげてほしい)予防についてお話しします。
また、「ペットショップで言われたんだけど・・」という方や、
「毎年やっているけど、何を予防してるの?」という方も、この項が理解の助けになればと思います。
(個々の病気についての説明は簡略化のため省略しました。
内容はあくまで予防を正しく理解していただくためのものです。)
ワクチンは、「病原体を撃退する方法を、体に学ばせる為の予行演習」といえます。ワクチンの成分は無毒化した病原体なのです。
それを注射することにより、体は(擬似)病原体との遭遇、撃退という経験をします。そして、病原体に有効な抗体(=武器)のデータを得るのです。
そうしておけば、万一本物の病原体に遭遇しても、速やかに抗体を量産し、病原体を撃退できるようになります。
これが、十分な抗体価をもつ、いわゆる免疫がついた状態です(抗体を介さない免疫もありますが、本筋からそれるので省きます)。
予行演習が不十分だと、体の免疫も不十分ですので、感染、発症の可能性が出てきます。
万全の免疫(抗体価)を保つには、一般的には子犬、子猫のときに2〜3回、その後は1年おきの追加接種が必要です。
移行抗体は、母犬の初乳に含まれる抗体です。生まれたばかりの子犬は、初乳を飲むことで移行抗体を体に「装備」します。
病原体が侵入すると、この移行抗体が子犬を守ってくれるのです。移行抗体は、この時期の子犬にとってなくてはならないものです。
しかし移行抗体は本物の病原体だけでなく、擬似病原体であるワクチンも破壊してしまいます。
ですので、移行抗体が残っている子犬にワクチンを打っても、前述の予行演習の目的が果たせなくなってしまいます(子犬が自分の力で撃退したわけではないので・・)。
しかし、初乳をしっかり飲めなかった場合や、そもそも母犬が抗体を持っていない(ワクチンを打っていない)場合、
子犬は無防備の状態になっているので、早くワクチンを打ってあげなければいけません。
つまり、移行抗体がなくなる時期がワクチンを接種すべき時期なのです。では、移行抗体はいつなくなるのでしょう?一般的には45〜60日目くらいまでです。
したがって、その頃一回目のワクチンを打てばよいことになります。
もし移行抗体が残っていれば、効果は不確実なことになりますが、その一ヵ月(30日)後に二回目を打てばまず確実です(この場合事実上はこれが一回目になります)。
そしてさらに一ヶ月後にもう一度ワクチンを打てば、確実に一カ月おき二回(もしくは三回)の追加接種をしたことになります。
場合によっては最後のワクチンはパルボウイルス単体のワクチンでもよいでしょう。
(移行抗体の消失時期が一番不確実なのが、パルボなのです。)繰り返しますが、接種時期は子犬と母犬のそれまでの状況によって左右されます。
子犬ごとにお話を聞きながら接種時期、回数を決めるのが一番です。
狂犬病ワクチンは、最後のワクチン接種のさらに一ヵ月後(生後約4〜5ヶ月位)、というのがわかりやすいと思います。 法律の「生後91日」をずいぶん過ぎてしまいますが、正当な理由が有りますので通常問題になることはありません。
また、初めて子犬を家に迎え入れたら、上記の接種時期になっていたとしてもすぐにワクチンを打つのではなく、一週間くらいたってからにしてあげてください。 子犬が新しい環境に慣れるまで待つ為と、飼主さんがワクチン接種による子犬の変化に気づけるようにする為です。普段の様子を知らなければ、違いもわからないでしょうから。
狂犬病ワクチンは、最後のワクチン接種のさらに一ヵ月後(生後約4〜5ヶ月位)、というのがわかりやすいと思います。 法律の「生後91日」をずいぶん過ぎてしまいますが、正当な理由が有りますので通常問題になることはありません。
また、初めて子犬を家に迎え入れたら、上記の接種時期になっていたとしてもすぐにワクチンを打つのではなく、一週間くらいたってからにしてあげてください。 子犬が新しい環境に慣れるまで待つ為と、飼主さんがワクチン接種による子犬の変化に気づけるようにする為です。普段の様子を知らなければ、違いもわからないでしょうから。